花粉症シーズン到来!食事から考える花粉症対策とは
春の訪れとともに、多くの人々を悩ませる花粉症の季節がやってきます。
毎年のように花粉に苦しめられている人も多いでしょう。
花粉症の対策としてマスクや薬の使用が一般的ですが、実は食事によって症状を和らげる可能性があることをご存じでしょうか?
今回は花粉症の基本的な知識や対策方法に加え、食事からできる花粉症対策について考えてみたいと思います。
目次
花粉症とは
花粉症の原因と仕組み
花粉症とは、植物の花粉が原因で引き起こされるアレルギー疾患です。
体内の免疫システムが花粉を異物と認識し、過剰な防御反応を起こすことで、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどの症状が現れます。
日本ではスギ花粉が最も一般的な原因で、その飛散時期がピークを迎えるのは3下旬~4月中旬ごろだと言われています。
(地域によっては差異があります)
その他にもヒノキやイネ科の植物や、ブタクサなども花粉症を引き起こします。
それぞれの花粉により症状が併発することもあるため、人によっては年間を通して花粉症に悩まされることも珍しくありません。
花粉症の症状
花粉症は単なる鼻炎にとどまらず、目や肌のかゆみといった症状もあります。
集中力の低下や睡眠の質の悪化を引き起こし、日常生活に大きな影響を与えることもあります。
そのため、早めの対策が重要です。
なお、花粉症の症状は基本的に生命に関わることはないとされていますが、花粉症と食物アレルギーが合わさった口腔アレルギー症候群などでは、まれにアナフィラキシー反応が生じるケースがあるそうです。
そのような場合は重症化のリスクもあるため、正確な診断・治療が必要となります。
主な花粉症対策
物理的な対策
マスクの着用
花粉症の対策として、まず重要なのが花粉の侵入を防ぐことです。
気候条件にもよりますが、マスクを着用することで花粉の侵入をおよそ7割防ぐと言われています。
メガネの着用
マスクと同様に花粉の侵入を防ぐことが期待できます。
通常の眼鏡であっても約6割の花粉を防ぐと言われており、花粉症用のメガネであれば更に高い効果が期待できます。
衣類の選び方
なるべく花粉が付きにくい素材(ナイロンやポリエステル)を選ぶことで、影響を最小限に抑えることができます。
また、静電気を抑えることで衣類に付着する花粉を減らすことも可能です。
柔軟剤や静電気防止スプレーなどを活用してみるのもよいかもしれません。
室内環境の整備
換気を短時間で済ませ、空気清浄機を活用することで室内の花粉を減少させることが出来ます。
帰宅後は衣類に花粉が付着しているためすぐに着替え、屋内に花粉を広げないようにする事も大切です。
医学的な対策
薬の服用(抗ヒスタミン薬)
花粉症による鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を改善する薬です。
アレルギー反応を引き起こすヒスタミンの働きを抑える効果があります。
また、予防として服用することで症状が出た際の負担を軽減することができます。
点鼻薬・点眼薬の使用
鼻づまりや目のかゆみを緩和します。
内服薬に比べ効果が限定的ですが、その分即効性があるため症状や状態に併せて使い分けることが重要と言えます。
舌下免疫療法
アレルギーの原因となる物質を少しずつ体内に吸収させることでアレルギー反応の軽減が期待できます。
長期的に体質改善を目指す治療法として注目されています。
ただし症状がひどい場合は、医療機関で適切な治療を受けることが重要です。
生活習慣の改善
睡眠不足やストレスは免疫バランスを崩し、花粉症の悪化につながります。
規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠時間を確保することで症状の改善が期待できます。
また、適度な運動をすることで、血流を改善し免疫機能を整えることができます。
継続することで呼吸器などの粘膜をきたえる効果も期待できるため、無理のない範囲で生活習慣に取り入れるとよいでしょう。
花粉症に良い食事・食材
花粉症の症状を和らげるためには、食事による体内環境の改善が鍵となります。
以下の食材を生活に取り入れることで、免疫バランスを整え、症状の軽減が期待できます。
抗炎症作用のある食材
花粉症の症状は、体内の炎症反応によって引き起こされます。抗炎症作用のある食材を摂取することで、症状を和らげることが可能です。
• 青魚(サバ、イワシ、サンマ など):青魚に含まれる「オメガ3脂肪酸」は炎症を抑える働きを持っています。
• 緑黄色野菜(ブロッコリー、カボチャ、ニンジン など):緑黄色野菜に含まれる「β-カロテン」には免疫力を高める作用があるため、免疫反応を正常に保つのに役立つとされています。
腸内環境を整える食材
腸内環境を整えることで免疫バランスが改善され、花粉症の症状を軽減する効果が得られます。
• 発酵食品(ヨーグルト、納豆、味噌 など):腸活でもよく耳にする発酵食品は、善玉菌を多く含んでおり、腸内環境を整える働きが期待できます。
• 食物繊維が豊富な食材(バナナ、サツマイモ、ゴボウ など):食物繊維は腸内で菌の餌となり善玉菌を増やす効果があります。
また、排便を促す作用もあるため腸内環境の改善が期待できます。
抗酸化作用のある食材
抗酸化作用のある食材を摂取することで、アレルギー反応の原因となる活性酸素の発生を抑えます。
• 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツ):ビタミンCが豊富な柑橘類は免疫力を高める効果が期待できます。
ビタミンC以外でも、数年前には「じゃばら」という柑橘類が注目されたりもしていましたね。
• 緑茶:カテキンが抗酸化作用を持ち、アレルギー症状を抑制する働きがあるとされています。
特に「べにふうき」などの品種に含まれる「メチル化カテキン」は強い効果が期待できると近年注目されています。
避けるべき食材
一方で、花粉症の症状を悪化させる可能性がある食材もあります。
例えばアルコールは、摂取することで血管を拡張し、鼻づまりを悪化させる可能性があります。
他にも添加物を多く含むスナック菓子やファストフードなどの加工食品は、腸内環境を悪化させることがあります。
また、過剰な糖分は炎症を引き起こす可能性があるため、甘いものの食べ過ぎにも注意が必要です。
まとめ
日本では60種類もの原因花粉があるといわれ、スギやヒノキだけでなく、シラカンバ、ブナ、ハンノキ、ケヤキ、コナラ、ブタクサ、ヨモギなど、1年中何かしらの花粉が飛んでいます。
今まで大丈夫だった人も、突然、発症することもありますので、「自分は大丈夫」と思わず、しっかり対策を立て予防することが重要です。
物理的・医療的な対策に加え、日々の生活や食事を意識することで、体の内側から花粉症を改善することが期待できます。
今年の花粉シーズンは、食事の見直しを取り入れながら、快適に過ごせるように工夫してみましょう。
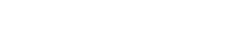












この記事へのコメントはありません。